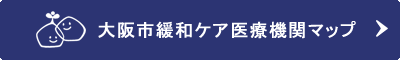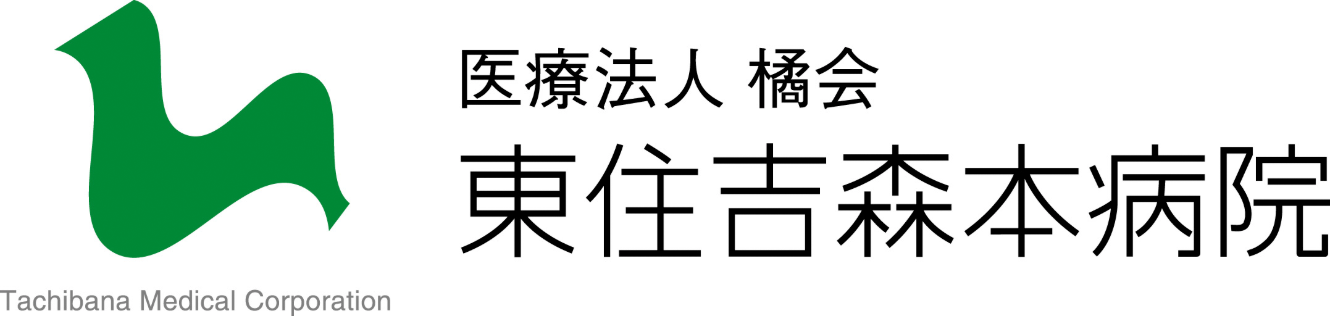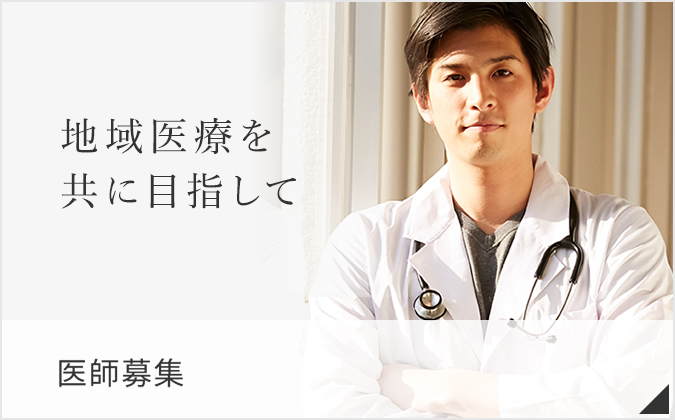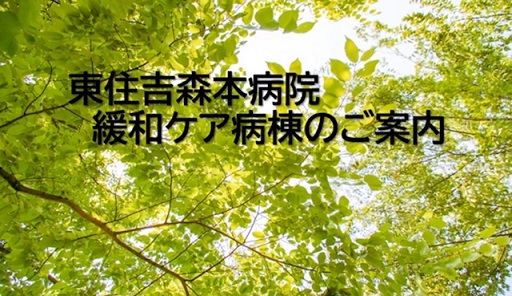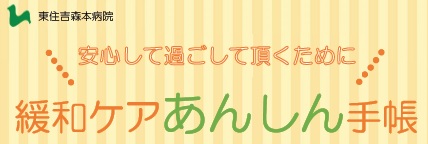緩和ケア
当院の緩和ケアとは
緩和ケア病棟
役割
当院の緩和ケア病棟は、「からだとこころのつらさを和らげ、穏やかに自分らしい生活を送れるお手伝いをする」ことをコンセプトに支援しています。当病棟では、症状コントロールに難渋し、専門的な治療と看護を必要としているがん患者さんを受け入れています。一般病棟では癌そのものの治癒を目指す治療を行いますが、緩和ケア病棟は治癒を目指すことを目標とするのではなく、癌の影響で出現してくる様々なつらさを和らげるための治療や検査、リハビリなどを行い、QOL(生活の質)の向上を目指す場所になります。つらさが和らぎ穏やかに日常生活を過ごせるようになると、患者さんとご家族の希望を確認しながら、どこでどのように療養したいかの相談も行っております。
実践
①症状緩和、②看取り、③レスパイト
実績
入院者数 171名
退院者数 174名
転帰:看取り 119名(68%)、在宅復帰 48名(28%)、転院 7名(4%)(2021.4.1~2022.3.31)
年間統計の詳細はこちら
緩和ケア病棟動画&パンフレット等
<<動画>>
緩和ケア病棟パンフレットはこちらからダウンロード緩和ケア病棟入退棟基準
入棟基準
- 悪性腫瘍と診断されている患者さんが対象です。
- 患者さんもしくは、ご家族が緩和ケア病棟の入院を希望されていることが原則です。
- 患者さんが、入院時に、病名、病状についてご理解されていることが望まれます。
- 化学療法や放射線治療など、悪性腫瘍に対する積極的な治療を終了しており、全人的苦痛の緩和を必要としている患者さんが対象になります。
- 重度の認知症、大声、暴力などで、他の患者さんの入院生活に影響があると判断される場合、入院はお受けしていません。
退棟基準
- 患者さんもしくは、ご家族が退院もしくは転院を希望しているとき。
- 病状コントロールができており、退院可能な状態であるとき。
- 手術、化学療法、放射線治療などの希望をされているとき。
- 対症療法でない治療がが必要な症状があり、その治療を優先する必要があるとき。
- 人に危害を加えるなど、他の入院患者さんに迷惑がかかり、共同生活が難しく病棟での管理が困難であるとき。
ひだまり食のご案内
丼物・麺類・軽食などから食べたいものを選んでいただきます。
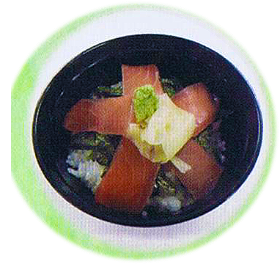



行事とりくみ

冬はクリスマスツリーを飾ります。

お正月は、福笑いの催し物を一緒に行っています。

花見シーズンの飾りつけなど季節ごとの展示で
四季を楽しんでいただいています。
スタッフ
緩和ケア内科部長 大場 一輝
|
消化器内科主任部長 藪さこ 恒夫
|
Q&A
Q:緩和ケア病棟とホスピスは違うの?
A:大きな違いはありません。 実施している治療やケアはほぼ同じです。延命治療を行わないで、がんによる痛みや息苦しさなどを治療・ケアしながら、最期までその人らしく 生き抜いていけるように家族と協力し、総合的にケアしております。
Q:緩和ケア病棟では、何をするの?
A:一般病棟と同様に、症状緩和のための治療やケアを積極的に行います。
ベッド上に寝て一日を過ごすだけ、ということはないです。回診や他職種カンファレンスもほぼ毎日実施します。一般病棟との大きな違いは、季節によって定期的にイベントを考え実施していることです。
Q:入院期間の決まりはあるの?最期(看取り)まで必ずみるの?
A:決まりはありません。
症状コントロールが出来たら、療養場所を在宅もしくは施設へ移行します。入退院を繰り返す場合もあります。もちろん看取る場合もありますが、緩和ケア病棟が最期の場となるわけではありません。一般病棟と変わりはありません。
Q:入院費用はどの位かかるの?
A:一般病棟で支払われる金額と変わりありません。
緩和ケア病棟やホスピスに入ると、ものすごくお金がかかるといった話をよく聞きますが、実際は一般病棟と同じく医療保険や高額療養費の制度を使うことができます。大部屋は室料がかかりませんが、個室では差額室料を頂いております。
Q:入院するまでにどれ位かかるの?
A:現状では、当院入院中の患者さんであれば、数日で受け入れ可能だと考えられます。
ただ、満床になった場合、どれだけの待機時間が必要になるのかは分かりません。外来通院中の患者さんや他施設から紹介の患者さんに関しては、まず、緩和ケア外来を受診して頂きます。その後、入院検討会議を経るため、入院中の患者さんよりは待機時間が長くなる可能性は高いです。この1年間の平均待機期間を見てみると、院内は6日程度、院外は8日程度です。
お問い合わせ
東住吉森本病院 がん相談支援センター
9:00~16:30(日曜・祝祭日を除く)
医療機関からのお問い合わせはこちら緩和ケア外来
役割
当科の外来は、2つの機能を有しております。1つは、緩和ケア病棟入院への窓口、もう一つは、症状緩和を行っております。まず、他院から緩和ケア病棟へ入院を希望される患者さんには必ず当外来を受診していただき、ご病状やご療養状況などを伺った上で、当病棟オリエンテーションをお受けいただき入院予約としております。今すぐに入院を希望される患者さんだけでなく、他院で抗がん治療を続けておられる方、在宅医や訪問看護師さんの支援を受けながらご自宅で生活なさっておられる患者さんに対して、痛みや呼吸困難、倦怠感といった身体的な苦痛や気持ちの辛さなどの精神的な苦痛を少しでも緩和していただけるよう、外来での緩和ケアも行っています。
外来担当表
外来担当表はこちらご相談はこちら
緩和ケア看護外来
緩和ケア看護外来の紹介
悪性腫瘍の患者さんと家族等を対象に、緩和ケア認定看護師の資格を有する看護師による「緩和ケア看護外来」を開設し、専門的な知見からサポートを行っております。具体的には、緩和ケア病棟利用に関する相談、からだや気持ちのつらさに関する悩み、医療用麻薬等を使用中の悩み、対がん治療に関する悩み等を、個々の療養生活状況をふまえ暮らしに寄り添いながらアドバイスをしております。
詳細は、こちらをご参照下さい。
緩和ケアチーム
役割
がん治療と同時に受ける緩和ケアは、主治医の他に、「緩和ケアチーム」が主に担当します。チームメンバーは身体面担当の医師、精神面担当の医師(非常勤)、緩和ケア認定看護師だけでなく、病院長が必要と認めた緩和ケアに精通した看護師や薬剤師、理学療法士、ソーシャルワーカーらで構成されています(表1)
表1 緩和ケアチームの職種とその役割
栄養士 患者さんの「食べる」を支えQOLを向上させるため食事量の調整・栄養管理を行います。| 医師 | 痛みや呼吸困難などの身体面の症状緩和を担当する医師と、気持ちのつらさなどの精神症状の緩和を担当する医師が、主治医へ治療に関するアドバイスを行います。 |
|---|---|
| 看護師 | 患者さんやご家族の日常生活についてのアドバイスを行います。 転院や退院後の療養生活についての調整も行います。 緩和ケア認定看護師 2名在籍 |
| 薬剤師 | 患者さんやご家族に薬物療法のアドバイスや指導を行います。 また、医療者に対しても専門的なアドバイスを行います。 |
| 理学療法士 | 日常生活維持のためのアドバイスやリラクゼーションを行います。 また、リンパ浮腫に対する治療も担当します。 |
| ソーシャルワーカー | 療養にかかわる助成制度や経済的問題、仕事や療養する場所、ご家族の社会生活についての相談などを担当します。 |
活動
週1回一般病棟をラウンドし、がん患者さんで対応困難事例や医療者が困っていること等ないか確認します。また、苦痛のスクリーニングで点数が高い患者さんに対するアドバイスも行っております。
実績
身体面52件
精神面 9件
スピリチュアル面3件
その他 2件
合計59件(2021.1.1~2021.12.31)
地域連携
緩和ケアにおける地域連携とは
緩和ケア病棟は、つらい症状を和らげる治療をするだけでなく、外来や在宅へのスムーズな移行を支援する役割も担っています。患者さんとご家族が、希望する療養場所で切れ目のない緩和ケアを受けられるように、当院救急センター及び在宅支援者らと協働し入退院支援をしています。
実績
- 在宅緩和ケアのバックアップベッド
- 救急センターと協働し断らない緩和ケアの提供
- 退院時共同指導
- 各種研修会の開催(PEACEや大阪市南部地区緩和ケア連携カンファレンス、東住吉緩和ケア学習会など)
在宅からの緊急入院受け入れ 75名(44%)、在宅からの予約入院受け入れ46名(27%)
(2021.4.1~2022.3.31)
緩和ケアあんしん手帳
当院では緩和ケアあんしん手帳を活用し、患者さんとご家族が安心してご自宅で過ごしていただけるよう、地域連携を行っています。
緩和ケア外来受診時に緩和ケアあんしん手帳を発行致します。
使用方法や役割などはこちらをご参照ください。
また連携パスシール・人生会議シールも下記より印刷可能です。
ご本人様・ご家族と、またかかりつけ医や訪問看護・ケアマネージャーなど在宅支援者と随時共有・見直しを行なってください。
※緩和ケアあんしん手帳は患者さんの治療経過など個人情報を含む重要な文章となります。紛失などお取り扱いにご注意下さい。なお緩和ケア外来受診患者さんに発行を強制するものではありません。
大阪市緩和ケア医療機関マップ
この緩和ケアマップは、大阪市がん診療ネットワーク協議会:在宅緩和ケア部会が作成しています。 患者さんにご自宅で少しでも快適で気持ちよい毎日をお送りいただけるよう、大阪市内の緩和ケアに対応できる診療所・病院を検索し、情報を得ることができるシステムです。(案内の詳細はこちら)